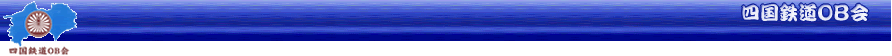香川支部三本松分会、中川 義博さん~東かがわ市・和三盆の由来~
讃岐の名産として知られる「三白」(塩・綿・砂糖)のうち、特に砂糖業は18世紀半ば、高松藩第5代藩主・松平頼恭の殖産政策から始まった。
頼恭は藩医・池田玄丈に製糖研究を託したが、志半ばで没する。弟子の向山周慶(1746〜1819)が後を継ぎ、薩摩から伝わった製糖法を基に改良を重ねた。
周慶は学問に励む一方、人徳厚く、薩摩出身の遍路・関良介を救ったことから良質なサトウキビ苗を得る。両者は師弟の如く30年にわたり試行錯誤を繰り返し、1790年に讃岐初の白砂糖を完成させる。この砂糖は「雪のように白く味も良い」と評され、大坂市場でも高く評価され和三盆の始まりとなった。
1803年にはさらに独創的な精製技術を確立し、生産が飛躍的に拡大。讃岐砂糖は輸入糖を凌ぎ、一大産業として高松藩財政を支える存在となった。
幕末期には国内流通の六割を占めるまで成長したが、周慶と良介は1819年に相次いで没し、波乱の生涯を閉じた。
その後も藩は砂糖産業を保護し、明治維新時には藩財政を潤す成果を残した。
松平家は周慶と良介を顕彰し、高松城内に「向良神社」を建立。明治期には官営工場や砂糖会社も設立されたが、外国産糖の流入により産業は衰退、1896年には民間会社も解散した。それでも和三盆の独特の風味は受け継がれ、高級和菓子や茶の湯の菓子として今日まで重宝されている。
戦後、戦災で焼失した高松の向良神社は再建され、また周慶の生誕地・東かがわ市湊にも新たな向良神社が創建され、関良介の墓とともに顕彰が続いている。
こうして和三盆は、先人たちの苦難と努力、そして人の縁から生まれ、今も香川の伝統として息づいている。
〇スライドショー
頼恭は藩医・池田玄丈に製糖研究を託したが、志半ばで没する。弟子の向山周慶(1746〜1819)が後を継ぎ、薩摩から伝わった製糖法を基に改良を重ねた。
周慶は学問に励む一方、人徳厚く、薩摩出身の遍路・関良介を救ったことから良質なサトウキビ苗を得る。両者は師弟の如く30年にわたり試行錯誤を繰り返し、1790年に讃岐初の白砂糖を完成させる。この砂糖は「雪のように白く味も良い」と評され、大坂市場でも高く評価され和三盆の始まりとなった。
1803年にはさらに独創的な精製技術を確立し、生産が飛躍的に拡大。讃岐砂糖は輸入糖を凌ぎ、一大産業として高松藩財政を支える存在となった。
幕末期には国内流通の六割を占めるまで成長したが、周慶と良介は1819年に相次いで没し、波乱の生涯を閉じた。
その後も藩は砂糖産業を保護し、明治維新時には藩財政を潤す成果を残した。
松平家は周慶と良介を顕彰し、高松城内に「向良神社」を建立。明治期には官営工場や砂糖会社も設立されたが、外国産糖の流入により産業は衰退、1896年には民間会社も解散した。それでも和三盆の独特の風味は受け継がれ、高級和菓子や茶の湯の菓子として今日まで重宝されている。
戦後、戦災で焼失した高松の向良神社は再建され、また周慶の生誕地・東かがわ市湊にも新たな向良神社が創建され、関良介の墓とともに顕彰が続いている。
こうして和三盆は、先人たちの苦難と努力、そして人の縁から生まれ、今も香川の伝統として息づいている。
〇スライドショー
向山周慶生誕の石碑
関良助の墓
向良神社
砂糖締車の説明文(三谷製糖にて) 次ページ実物
砂糖締車(三谷製糖にて)
和三盆圖會(わさんぼんずえ)(三谷製糖にて)